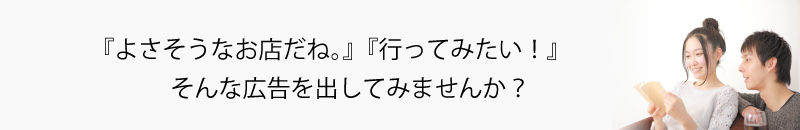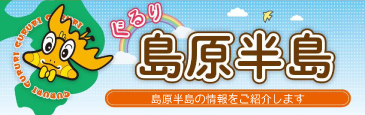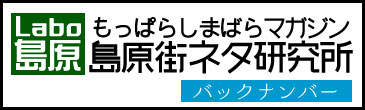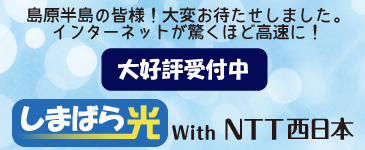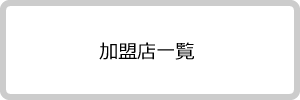記事
2.192018
松尾先生のおはなし・島原の歴史 第2回おとうの見た合戦
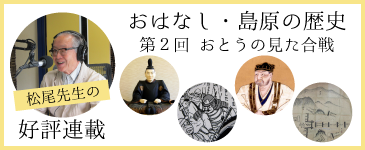
〈はじめに〉
有馬の殿様島原半島は肥前の国から有明海に突き出たところにあります。まわりを海にかこまれ、一つの独立した地域になっています。
この地を有馬氏が長く支配してきました。
そのもとは藤原経澄といい鎌倉武士で、地頭となってやってきました。やがてその子孫は土地の名をとって<有馬>というようになりました。
戦国時代は力がある者が領地を広げていきます。島原半島をまとめた有馬の殿様は隣の大村を破り、松浦・平戸も占領して肥前の国の半分をまとめました。
こうして戦国大名の地位をがっちりと固めたものです。その頃です。
一艘の南蛮船が種子島へ、その時から日本の国は大きく変わっていくのです。
そして1567年には口之津へ初めてポルトガル船が入港しました。島原にもヨーロッパ文化が広まっていきました。
1.キリスト教が伝わる
舌がとろけるような甘い砂糖菓子やカステラ。米の飯とずいぶん違うパン。
人の血かと恐るおそる飲んだブドウ酒。口や鼻から煙を出してすうタバコ。遠くのものが手に取るように近くに見える遠眼鏡。
冬でも暖かいラシャやカッパなど。それは驚くばかりです。なかでも鉄砲はすごい威力を発揮しました。
遠く離れたものも、空を飛ぶ鳥でも百発百中射止めることができるからです。武士にとってはこれほどない武器になったのです。
有馬の殿様がこの鉄砲と火薬を買い入れたことはいうまでもありません。
また湊にはキリスト教の神父さんもやってきました。
島原の村々は土地もせまく、貧しい村人が多いので、そんな人へ分け隔てなく人々を大切にするキリスト教の教えはぐんぐん広まっていきました。
教会だけでなく、キリシタンの学校であるセミナリヨやコレジオも開かれ、有馬の地はキリシタンの天国のようでした。
2. 佐賀の龍造寺
北となりの佐賀に龍造寺隆信という殿様がそのころ力を伸ばしていました。
佐賀はもともと大きな平野があるところで、農業も盛んで人口も多く、豊かなところです。
佐賀の殿様はまわりへどんどん領地を広げていきました。やがて九州全土を征服して強力な国を築こうとの考えです。
そのころの殿様はだれでも同じような考えを持ち、その夢の実現のために戦いを繰り返していきました。
島原半島にこもって独立を守っている有馬の殿様は、佐賀の殿様と手を結ぶか、戦うかを決めなくてはなりません。
「おとう、合戦が始まっとげな」。
「なんて、合戦があっとてや。そがんいえば、柏野道ば早馬が、よう、走ってたもんね。」
久吉は水の権現の神主さんから聞いたことを話しました。
「佐賀ん殿様が大村まで占領して、もうすぐ島原さん攻めこむとげな。
そいで有馬ん殿様も合戦ばするごてきめらしたとて」
ここ水の権現は、久吉たちの村・杉谷の山麓にあるお宮です。清水がコンコンと湧き出て村の水源となっています。
神主さんは村一番の知恵者です。
「そんなら。早よう江里ん山おくへ逃げにゃんたい。とばっちりばうけて殺されてしま うぞ。」
3.おとう合戦場へ
有馬晴信は戦うことに決めました。とはいっても龍造寺軍は大軍です。
とても勝ち目がありません。そこで薩摩の島津の殿様に助けを求めました。島津の殿様は龍造寺軍を破って一気に北九州までも領土を広げようとの考え、このさそいに乗り出しました。
一方、有馬殿様は領地の守りを固め、兵力を増やすかたわら村々から農民を集めることにしました。村に住んでいる久吉のおとうも武士の手伝いを命令され馬といっしょにかり出されました。
「おとう、無事に帰って来いよ。」
残された久吉は、おかあとおばばを連れて山おくへ逃げ出しました。そして早く戦いが終わり、おとうが元気で帰ってくることを祈りました。
1584年の春の始めです。龍造寺軍は神代の浜に上陸しました。
大村を攻めほろぼした一隊と合流した2万5千もの大軍は三会村の寺中の城跡に陣地を構えました。
助けに来てた島津軍は須川(西有家)について有馬氏に加わり、島原村の森岳に陣を構えました。
その中にはおとうたち農民も沢山います。それでも兵力は6千人にしかなりません。
三会の方を見ると、沖田原の先だけでなく山手や海手にも龍造寺軍でいっぱいです。
「ウへ~、佐賀んもんは多さ。こりゃ、負けっとじゃなかろうかい。」
わたされたヤリをかかえて、おとうはふるえています。
龍造寺軍は3手に分かれて森岳に構える有馬・島津連合軍を取りつぶそうとの考えです。
息子の龍造寺政家に鍋島直茂が加わった一隊が山手から杉谷方面をねらい、海手には江上家種隊がいます。
総大将の龍造寺隆信は大部隊をひきいて真正面にどっしりとかまえています。
4.沖田原の戦い
迎えうつ連合軍は森岳の本陣に武将を集めて作戦をねっています。かがり火が赤々と燃え、その中で有馬晴信が命令しています。
「原と日野江の城は、我が家来・堀に任せておるので安心してもらいたい。山手の水の権現には新納忠元殿、さらに山手の折橋には猿亘、越中守殿をひそませる。
本陣には島津の御大将と拙者がひかえ、その先頭に赤星軍を立てる。海上には船13そうを率いる安富越中守が備えるのだ。」
夜が明けました。合戦の時が近づきます。心配で眠ることが出来なかったおとうたちも集められて、総大将の有馬晴信が命令をくだしました。
「竜造寺隆信は優れた武将である。普通の戦いでは勝ち目はないのだ。良いな、敵よりせめられても、味方から攻撃をしかけてはならぬぞ。
攻撃の合図でいっせいに打ちかけるのじゃ。打ったらただちに弓、鉄砲をすてて刀で切りかかれ。
全員心を一つにして、この馬印より前に出て、大活躍してもらいたい。この命令にしたがわぬものがあったら、 たたっ切ってしま うぞ。よいな。」
「オーッ」、おとうも手にしたヤリを高くふり上げて力いっぱい叫びました。
連合軍の意気は一度に盛り上がりました。
朝もやの中を竜造寺軍が森岳を目指して一直線に進んできます。赤や青、黄色と色とりどりの旗やのぼりがひらめいています。
馬のいななきや合図のホラ貝が聞こえてきます。田んぼにひかえているおとうは、ブルッと身ぶるいしました。
ザク、ザク、ザク、、、、進軍する大軍の足音が地鳴りのようです。
戦をさけて山おくに逃げこんだ久吉は高い木にのぼってはるか下に広がる合戦のようすをながめています。
三会から沖田原には、何百もの旗やのぼりが立ち森岳のほうへ動いています。森岳のまわりにはクルスの旗が4,50本ひるがえっています。
5.火をふく鉄砲隊
「こりゃ、佐賀んもんには勝てんばい」。久吉の目にも、連合軍の不利が見えます。
龍造寺の大軍は沖田原へさしかかりました。それはちょうど、大蛇がゆっくりと進んでいくようです。
すると、その大蛇が止まったように見えました。なにしろ沖田の田んぼは杉谷のいくつもの川がつくった湿地帯です。
そこにはほそい道が一本とおっているだけで、数千もの大部隊が一度に入りこむとなかなか思うとおりに進めないのです。
このようすを森岳の上からじっとながめていた有馬晴信は、「まだじゃ。まだ、待つのだ」と、はやる武将たちをおさえ、もっと引きよせて、山手と海手の部隊が完全に準備するまで待てというのです。
少ない兵力の連合軍は、この湿地で一気にほろぼす計画です。チャンスがくるのをじっと待ちます。
「うてっ!」。
攻撃の合図が出ました。湿地のあちこちにひそんでいた有馬の鉄砲隊が一度に火を吹きました。
バーン、バ・バンー、バーン、、、、何百という鉄砲玉がとび出しました。
たちまち百人あまりが倒れ、武将をのせた馬が驚き飛びはねています。大混乱です。
このために、押しよせる部隊は前に進めず、後に引けず、湿地へ逃げだすと足をとられるし、大混乱が続きます。激しい鉄砲隊の攻撃は続きます。
ワーッ、ワーッ!
かけ声とともに赤装束のヨロイカブトに身を固め、ヤリと刀を突きたてた集団が森岳をかけ下りました。
有馬第一の部隊・赤星隊です。
「今こそ、龍造寺のヤツめを滅ぼすときだ!」。がむしゃらに突き進みます。
鉄砲隊に進路をはばまれて混乱しているところへ赤星隊が切り込んできたのです。
身をさけるところもない湿土の中ではどうすることもできず、龍造寺軍は死者を増やすだけです。
この様子を見た薩摩の総大将・島津家久はほら貝とタイコをたたき、海手の伊集院軍と山手の新納軍へ攻撃の命令を出しました。
連合軍の全員が打ちかかっていきます。おとうもヤリをめちゃくちゃに突き出しています。見る間に沖田の湿地は血で染まり、あたり一面に死体の山ができました。
「命を惜しまず、打ちかかれ!」
6.龍造寺隆信の戦死
龍造寺隆信は部隊を立て直そうと先頭や後陣へ命令を出しますが、混乱の中ではそれも伝わりません。武士たちはどうすることもできずバタバタと倒れていきます。
負け戦の中ですが、龍造寺隆信は小高い土手にイスを置きどっしりと座っています。身近に従えている武将と小姓だけが集まり、戦いの成り行きを見守っています。
もはや運命が近づいたことを知りました。長かった戦いに明け暮れた人生を思い浮かべているのでしょうか。
合戦の中とは思えないどっしりとかまえた姿です。総大将を取り囲んでいる人の輪が一人、二人と倒れていきます。
しかし腰かけたままの大きなからだはびくともしません。もう守る家来も少なくなりました。
そこへ長身の武士が刀を下げたままひざまづきました。
「拙者は島津の家臣・川上左京と申します。お命、頂戴いたします。」
龍造寺隆信はかすかにうなづいたようです。そして、その大きな体が崩れ落ちました。
3月24日昼過ぎのことです。
「敵の大将を討ち取ったぞ!」
それを聞いた連合軍は、カチドキの声を上げました。
「エイ、エイ、オー!」
総大将の死で龍造寺軍は総崩れとなり、我先にと逃げだしました。雨も降りだし始めた中を北へ北へと逃げ去りました。
7.帰って来た おとう
勝利の報告はすぐ有馬の城下へ伝えられました。町では鐘が打ち鳴らされて人々は勝利の喜びをかみしめました。
教会にこもって祈っていた神父さんたちは感謝のミサを始めました。
久吉たちは雨にぬれながら日暮れの山道を家へと急ぎました。暗やみの中を、おと うが帰ってきました。
「ねえ、おとう。合戦はどがんじゃったと?」「そりゃ~、ひでぇーもんじゃったぞ。沖田ん田にゃ数えきらんぐらい死体が浮いちょった。地獄の血の海のごたったい」
おとうのひげボウボウの顔は疲れ切っています。着物は泥で汚れ、血あかがついて臭いにおいさえします。
「おとう、早よう食べろよ。」おかあが差出すカユを、なんばいもおかわりしながらおとうは話します。
「合戦はひでぇもんじゃった。佐賀に使われた三会んもんは、負け戦じゃっけん、巻き添えば食ってオダブツじゃ。そいで三会ん五郎八どんたちゃ、どがんなったろかい。あした、探しにいくバッテン。」
夜がふけます。
ますます雨がひどくなりました。龍造寺軍に加わって亡くなった3千人の涙雨でしょう。
「なんで合戦ばせにゃいかんとじゃろかい。おいたち百姓は米ばつくっちょっとが一番よか」
いろりの火に照らされたおとうの顔にやっと安らぎが戻っていました。
(次回は「いのちあるかぎり」)
先生の紹介
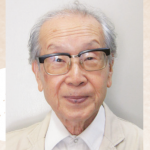 松尾先生は昭和10(1935)年島原市生まれ。
松尾先生は昭和10(1935)年島原市生まれ。
島原城資料館専門員、島原文化財保護委員会会長。
『島原の歴史については松尾先生に聞け』と言われる島原の生き字引的存在。
著書に『おはなし 島原の歴史』『島原街道を行く』『長崎街道を行く』など。
※FMしまばら(88.4MHz) 毎週金曜日 10:30~「松尾卓次のぶらっとさらく」放送中!
過去の記事はこちら。
松尾先生のおはなし・島原の歴史 第1回くれ石原をかけめぐる
松尾先生の島原街道アゲイン 最終回 「深江~安中」
松尾先生の島原街道アゲイン「有家~布津」
松尾先生の島原街道アゲイン「北有馬~西有家」
松尾先生の島原街道アゲイン「口之津~南有馬」
松尾先生の島原街道アゲイン「南串山~加津佐」
松尾先生の島原街道アゲイン「千々石~小浜」
松尾先生の島原街道アゲイン「吾妻~愛野」
松尾先生の島原街道アゲイン「国見~瑞穂」
松尾先生の島原街道アゲイン「三会~湯江編」
松尾先生の島原街道アゲイン「島原市街地編」
島原の歴史50選「第6回 激動の時代」
島原の歴史50選「第5回 明治の新しい世」
島原の歴史50選「第4回 しまばらの江戸文化」
島原の歴史50選「第3回 松平時代」
島原の歴史50選「第2回 切支丹時代」
島原の歴史50選「第1回 原始・古代・中世」
「人物・島原の歴史シリーズ 第6回 未来へ続く人々」
「人物・島原の歴史シリーズ 第5回 新しい時代を切り開く」