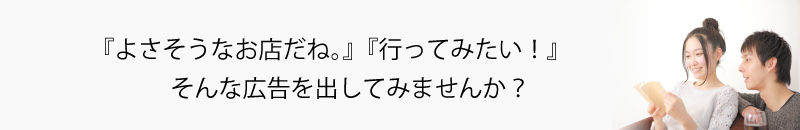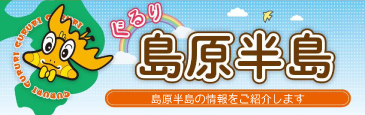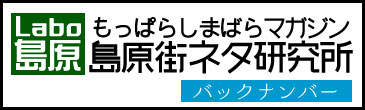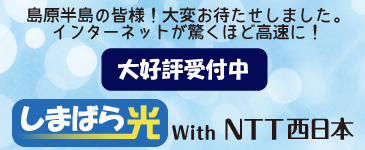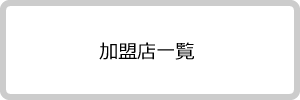記事
4.192017
松尾先生のぶらっとさらく島原 第7回 口之津~南有馬
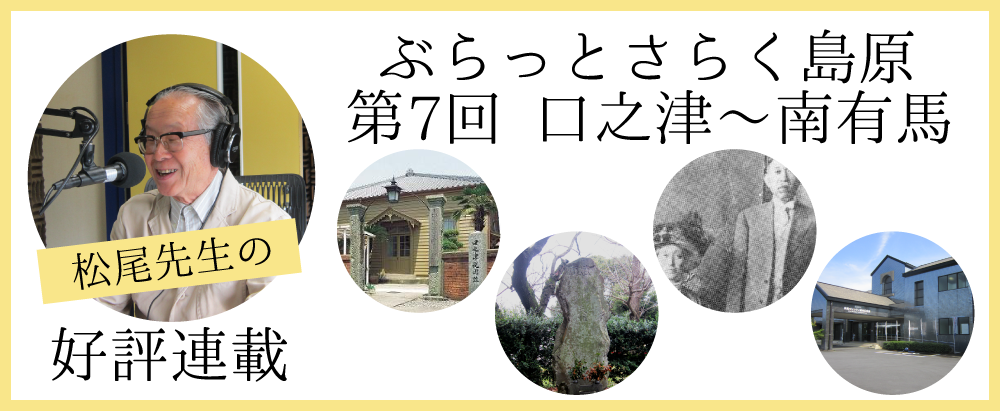
はじめに
口之津は港で栄えた町である。有明海の入り口にある津(港)ということからその名が生まれたろう。
有明海は大きな内海で、沿岸に熊本、柳川、佐賀の町があり、そこへ?がる口之津は格好の港である。
おまけに入り口には大きな渦巻きが生じる難所の早崎海峡があり、潮待ち、風待ちの港が重宝がられた。
16世紀以来南蛮貿易の基地となって、多くの外国船が入港し世界へと開かれる。
1.口之津港
日本の裏側からも宣教師や珍しい品物、素晴らしい学問技術がやって来た。
島原の乱以後この海外交易も途絶えるが、太平が続いた江戸時代は沿岸航路の一拠点として発展する。
明治になると三池炭の輸出港として再び世界へと開かれていく。同時に多くの人びとが海外へはばたき、永野万蔵をはじめ、各地で活躍する。
今でも船員として世界中の海で働いている人が多い。大屋の埋立地には海技学校があって、口之津だけでなく近隣からも海にあこがれる若者が学んでいる。
町を歩いているとあちこちにその痕跡がある。南蛮船来航地、瀬高観音、口之津灯台、海の資料館、キリスト教会跡などなど。
2.口加高校
街道は国道251号線となり坂道。登りきったところから旧道へ進むと、口加高校前となる。
小川を挟んでこちらが加津佐町、向こうが口之津町で、「なるほど口加高か」。
口之津は開明的な地であったから、電信・電話・郵便などと文明の利器の導入が早かった。
1902年には永野仲蔵によって口之津女子手芸学校が開かれた。島原の女子手芸学校に1年遅れただけ。
やがてここ久木山に校舎を移し、1年生31人、2年生14人、専修科17人と拡張する。
その後口之津・加津佐両村組合立となり、校名も「口加」がつき、1937年には県立口加高女となる。
戦後の学制改革で、男女共学の高校へと発展する。ここも創立100年を超えた。卒業生にはそうそうたる人物がいる。
町中心部へと足を進める。いずこも同じで過疎化が進み、空き家と空屋敷が増えてきた。
港が見えだす。
かつては大きな三井倶楽部があり、テニスコートも造られ、商店も並んでいたそう。
口之津は三井のドル箱で、三池炭で今日の三井を創り上げる。
三井の理事長で経済界の重鎮となった団琢磨もしばしばここを訪れ、テニスを楽しんだこともあろう。
支店長の中にはあとで大臣になった藤村義朗がいた。
3. 海の資料館
街道を離れて港を半周、その入り口にある口之津歴史民俗資料館を訪ねる。
新開、焚場、仲町、大泊と港に沿って道が走り、古い家がどっしりと構えている。
ここの地名といい、家の造りといい、港で栄えた頃がしのばれる。旧家はそれぞれ屋号を持っていて、今でも通用している。
赤塗の橋、南蛮大橋を渡って海の資料館に着いた。明治初年に建てられた税関の跡をもとに開き、さらに拡張したもの。
さすが港で栄えた町だ。
この建物といい敷地や船着き場をよく保存し活用している。また展示物もよく収集されている。
港とともに歩んできた歴史と海にかかわりを持って暮らしてきた口之津の人の生活がよくわかる、見ごたえのある資料館である。
口之津の町がさらに繁栄する契機になったのが、三池炭の輸出である。明治維新後は官営企業として新政府が開発していく。
その販売を三井物産が引き受け、海外までも輸出するようになる。三池(大牟田)の浜は遠浅で、大型船が入港できなかった。
それで石炭は団平船で口之津まで運び、ここで積み替えて送り出していた。この業務を口之津の素封家南家が請け負い、多くの人夫を雇う。
働き口を求めて各地から人が集まり町も繁栄していく。人口も1万人を超え、商店が279軒と賑わっていた。
最盛期には年間輸出石炭92万トン、貿易額350万円、入港汽船2,900艘と記録されている。
4.万蔵と力松
石炭とともに人もこの港から世界中に旅立つ。
その人たちを“からゆきどん・からゆきさん”と呼ぶ。
明治になって門戸が大きく開かれると外国へも働きに出た。
その一人が永野万蔵で、力松である。
永野万蔵は、1887年、カナダに入国。
日本人移民第一号となった人である。
実業家として成功し、サーモンキングとも呼ばれるほどであった。
日本人会会長としても幅広く活躍した人でもある。不幸にして結核に侵されて口之津で養生するが、ここで波乱の一生を終わる。
活躍したバンク―バーの近くにはマウント・マンゾ―と名付けられた2000mの山があり、日本移民100周年を記念して日加友好の絆として命名されたもの。
名もなく、かの地で一生を終わった人もある。力松の話は悲しい。
力松は14歳の時、船乗りとして働いていた熊本・川尻船が天草へ航海中に遭難してヘレベンという南方の小島に漂着した。
マニラ、そしてマカオへ送られてイギリス人に保護される。
1837年に同じ漂流民の尾張(名古屋)の音吉たちと共にアメリカ船モリソン号で浦賀(神奈川県)に送還されるはずだったが、幕府は異国船打ち払い令に基づいて砲撃を加え入国を拒む。帰国を断念しなければならなかった。ホンコンに帰り、アメリカ人ウイリアム神父の元で生活。
その後アメリカ人と結婚、3人の子にも恵まれた。ここで歴史が動く。
日本が開国するようになり、外国船が続々とやってくる。
イギリス艦隊の通訳として長崎へ。
長崎奉行川村対馬守と会談のとき口之津出身のことを話し、島原藩へ調査を依頼したそうだが…その結果は記録にない。
また祖国に捨てられたのか。
5.山洞・カンゴ石
大屋から山道となる。
南有馬との境に大きな宮崎鼻という崖があるので道は迂回する。その手前住宅地の裏手に、山田右衛門作屋敷跡がある。
近くには与茂作川もあって、筆洗いの川という。右衛門作は南蛮絵を学び有馬家臣で絵師になった人。
島原の乱時には原城に籠城し、あの名高い「陣中旗」(四郎の旗)を描く。
山道を歩いていると南有馬町に入る。山洞集落で、御堂があるので立ち寄る。
大石をご巡視のお殿様が急に腹痛となり、傍らの石の上に殿様を休ませて随行の家臣たちが一心に病気回復を祈ったら病気も回復したそう。
それでこの大石をカンゴ石といい、今日も地区の人が祭っていらっしゃる。
この山手に夏吉集落がある。そこには伊之助という剛の者がいたそうだ。
高岩山のみそ五郎と力比べをさせたらどうだろうと夢話を考えながら歩く。
ここの伊之助やみそ五郎、加津佐にもみそ五郎がいたそうで、山手集落には巨人伝説がある。
それを西有家の人たちは上手に町おこしにみそ五郎を利用している。
6.原城跡
古地図を見ると、この一帯は海水が入り込む低地である。
原城はもとは春の島といわれ、南東部に突き出た周囲3キロの岬を利用した平山城である。
そこに目を付けた有馬貴純が1496年に日野江城の出城として築いたもの。ここは天然の要害で、有明海から流れ込む海水が城の周囲の堀となる。
干潮時には泥沼化して、そこへ田野川が流れ込んで大きな入江を造り出す。東側は30メートルの断崖絶壁で、そこに本丸がある。
北に二の丸、三の丸がせり出し、それぞれに出丸が造られ丘陵全体が要塞となっていた。
ここに1637年暮れに一揆軍が立てこもる。それが島原の乱である。
「松倉記」によると、その数島原側2万3881人、天草側1万3000余の合計3万7000人が結集したという。
しかし実態は3万に満たなかったろう。その半数は女、子供老人たちであった。
それにしてもこの農民たちが13万もの幕府大名軍を相手に3か月も戦い続けるのである。
彼らは庄屋を中心とした村共同体の結束とキリシタン信仰の力、天草四郎を総大将に祭り上げた浪人たちの戦術と戦法の巧みさで、単なる農民の一揆と異なる一大反乱へと高めていく。
7.大江の首塚
山道を下り着いたところが吉川地区。権現橋たもとにアコウの木がある。
熱帯の樹木で、口之津早崎に大群生地があり、北串山から有家までの浜によくみられるものだ。
平均気温が16~17度と温かい地で、今でも甘蔗を植え付け黒砂糖を作る家もある。
国道251号線に出た。古野憩いの公園がある。
吉川小学校長の古野清秀先生の頌徳碑がたち、住民から大変慕われた人である。
この子孫さんが古野電気を起こし、世界的な発明”魚探”を成功させた人であることはご承知の通り。
大江の町中を歩く。田町川向うに八幡神社がある。境内に反乱者の首塚がある。
3分してここと天草、長崎に葬った。
「血が流れて川をなし、草木も色あせて虫が山野を覆い、疫病は流行して五穀も稔らず…」と、乱後の村は荒廃した。
代官として派遣された鈴木重成は亡くなった人の霊を供養しようと、島原天草の僧を招いて3日3晩にわたって盛大な法要を営んだ。
そしてこの供養塔をたてた。
神社の周りには漁港があり、わかめの養殖や天草沖へも出漁している。
かつて藩主の巡視時は、ここで鯛網をご覧なっていたそうで、また天草や熊本の通路であった。
幕末には吉田松陰先生がこの地に来て、船頭の家に一泊して島原へ向かった。
8.原城を訪れた人たち
島原の乱については多くの本があり、いろんな人が訪ねて記録している。
吉田松陰は1853年に来た。
「原の古城を巡見する。本丸、二の丸、三の丸歴々然たり。皆、畑となる。孤松の下に板倉内膳正重昌の碑あり」などと書く。
あっけない。
本草学者の古河古松軒は「古戦場を見ること、古を思う情が浮かんで面白く」と筆を進め、「板倉重昌は智才の良君だったが功を焦り、合戦の失敗で討ち死にしたことは惜しい」「松平信綱は情勢をよく見、必死の賊軍を見定めて、兵糧攻めにしたのは名君というべし」などと具体的。
1812年には伊能忠敬が来ている。浦田の老人治右衛門の案内と詳しい説明を受けている。
1932年には種田山頭火も来ているが、日記には「原城跡を見て歩けなかったのは残念だった」と一言のみ。勿論句も残していない。
私も本丸に立つ。そして歴史を思考する。雲仙岳から有明海、湯島、そして天草と360度展望する。
いつ見ても美景である。この穏やかな地で数万の人命が奪われたとは…
サンチャゴ!彼らの叫び声が聞こえる。
(次回は北有馬から西有家まで)
先生の紹介
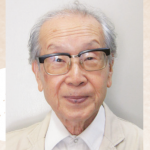 松尾先生は昭和10(1935)年島原市生まれ。
松尾先生は昭和10(1935)年島原市生まれ。
島原城資料館専門員、島原文化財保護委員会会長。
『島原の歴史については松尾先生に聞け』と言われる島原の生き字引的存在。
著書に『おはなし 島原の歴史』『島原街道を行く』『長崎街道を行く』など。
※FMしまばら(88.4MHz) 毎週水曜日 12:05~「松尾卓次のぶらっとさらく」放送中!
過去の記事はこちら。
松尾先生の島原街道アゲイン「南串山~加津佐」
松尾先生の島原街道アゲイン「千々石~小浜」
松尾先生の島原街道アゲイン「吾妻~愛野」
松尾先生の島原街道アゲイン「国見~瑞穂」
松尾先生の島原街道アゲイン「三会~湯江編」
松尾先生の島原街道アゲイン「島原市街地編」
島原の歴史50選「第6回 激動の時代」
島原の歴史50選「第5回 明治の新しい世」
島原の歴史50選「第4回 しまばらの江戸文化」
島原の歴史50選「第3回 松平時代」
島原の歴史50選「第2回 切支丹時代」
島原の歴史50選「第1回 原始・古代・中世」
「人物・島原の歴史シリーズ 第6回 未来へ続く人々」
「人物・島原の歴史シリーズ 第5回 新しい時代を切り開く」