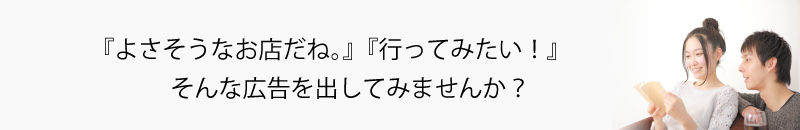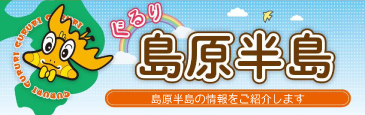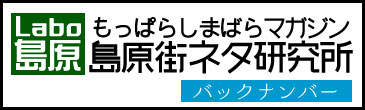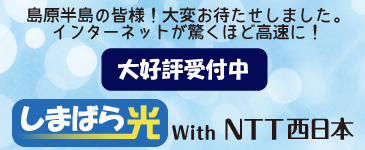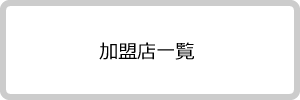松尾先生は昭和10(1935)年島原市生まれ。
島原城資料館専門員、島原文化財保護委員会会長。
『島原の歴史については松尾先生に聞け』と言われる島原の生き字引的存在。
著書に『おはなし 島原の歴史』『島原街道を行く』『長崎街道を行く』など。
※FMしまばら(88.4MHz) 毎週水曜日 12:05~「松尾卓次の島原歴史探訪」放送中!
記事
10.212015
松尾先生の島原の歴史50選「第4回 しまばらの江戸文化」
「??十景」という島原名勝を詠んだ漢詩がある。180年も前に島原8代藩主忠公侯の作だが、その十景が今もほぼ残る。
毎年秋の一夜に島原城薪能が開かれる。きやびやかな能楽が江戸時代と同じように演じられる。
島原は変わった、変わったといわれが時を超えた文化と歴史が今も伝わっているのだな。
今回は、その島原の江戸文化について紹介しよう。
1.島原名勝・??十景
「??十景」
森城朝輝~朝日に輝く森岳城 ― 今もそうです、毎朝、目にしてます
猛嶋秋月~猛島に登る秋の月 ― これまた、昔のまま
長浜晴嵐~長浜の晴れた日の霞 ― 長浜海岸はいつも美しい
眉山暮雪~眉山の夕暮れの雪景色 ― めっきりこのところ雪景色が見られないが…
霊丘夕照~霊丘の夕映え ― このところ開発されて、自然が失われた
萩田落雁~沖田に舞い降りる雁 ― まず雁がいない、沖田の田圃が少なくなった
柳浦皈帆~九十九島に帰る帆掛け船 ― 今ではフェリーとエンジン付きの漁船
西方晩鐘~西方寺の暮れの鐘 ― 西方寺も晩鐘も健在だが…
菰松夜雨~菰松に夜降る雨 ― 湿地に生える小木に降る雨か、どこの事かな?
紫海漁火~有明海の漁火 ― 漁火はなくなったが、今では対岸が燈火は美しい
天保九戌季春 源 紫州(忠侯)
??(しょうよう)とはぶらっとさらく(散歩)こと。その名をつけた別荘が田町門外にあって、板倉八右衛門勝彪(楽山)の所有。有明海を望むここは、藩主を始め文人墨客が集まるサロンであった。
天保9(1838)年8代藩主忠侯が島原名勝10か所を詠んだ扁額が伝わる。
さすが島原第一の文化人のお殿様だ。ところでどこかお分かりかな?
2.文化を高めた雲泉・温山・佐之
(釧雲泉)島原領内から出て江戸で高い評判となった南画家がいた。
千々石村(千々石町)出身の釧雲泉である。
雲泉は1759(宝暦9)年生まれ。
幼少時から絵が好きで、温泉山の寺へ出されるが続かず、長崎へ出て中国人から南画と中国語を学ぶ。
やがて大坂や京都を巡り、江戸へと放浪の旅をしながら各地の風景を描いたその絵は今も高い評価を得ている。
この頃江戸では町人文化が盛んで、雲泉は当時一流の文化人と交際して益々その名を高めていった。
田能村竹田、頼山陽、亀田鵬斉などそうそうたる画家や詩人から好まれた。
さらに越後(新潟県)へ行き、良寛和尚のいた出雲崎に滞在。
そこで53歳の生涯を終わる。
(川北温山)寛政5(1793)年島原藩校・稽古館が創立すると学者が続々現れる。
初代教授が岩瀬行言で、江戸でも名のある儒学者であった。
その後を継いだのが川北温山で、幼少時から行言に学ぶ。
頼山陽や安積艮斎などとも交際し、その名が通る。
その著書「原城紀事」は島原の乱を調査し、その本質を研究した書で全20巻、江戸で刊行されている。
その後もしばしば出版されて島原の乱の研究書として名高い。
(賀来佐之)島原藩庁はシーボルトから医学を学んだ賀来佐之を招いて、済衆館の教授に任命した。
彼は医学だけでなく西洋科学も指導している。
島原第一の科学者である。
その一つが薬草の研究であり、薬草園跡がそう。
藩では城内にあった薬草園をさらに充実させようと、眉山の麓の山林を開発して1haに拡大した。
1846(弘化2)年に完成した。
さらに弟の睦之(睦三郎)を呼び寄せて、島原半島の薬草調査に回らせた。
睦之は528種の薬草を採取し、彩色図鑑『島原採薬記』にまとめた。
その後も薬草を求めて諸国を歩いた。
3.島原藩の能楽
700年前に始まった能楽は室町幕府の保護もあって武士階級に広まっていく。
豊臣秀吉は能に打ち込み、稽古するだけでなく、金春・観世・宝生・金剛の大和4座の役者たちに給当米を与えて保護し、支配下に置く。
この保護政策が次時代へ受け継がれていく。
江戸時代になると、能楽は幕府の式楽となる。
幕府の公式の宴には必ず能楽が開催されていた。
将軍の代替わりなど公式の行事にほとんど能楽が関わり、能楽自体が幕府の欠かせない行事となっていく。
島原松平家は譜代大名であり、家康以来の信頼が厚かったので、よく招かれて将軍に近侍して共々能を楽しんでいる。
諸大名も能役者を雇うようになる。
忠房藩主はお能好きのお殿様でその真髄を極め、宝生大夫より「能之覚」を賜われる。
忠房藩主はよく能を催して、その数30回以上が記録に残る。
時には藩主は一部の町人や農民を招いて共々慶事を祝った。
これを契機に豪商や豪農は教養として学び、中には招かれて藩主の前で演ずることもあった。
「謡」が広く愛されて庶民にまで広まっていく。
島原藩内の豊後高田・算所村には能楽や歌舞伎、舞を専門にする芸能集団があって生業としていた。
藩主に招かれて演じ、呼ばれて各地で上演していた。
島原にはそのような能楽の下地が存在したのである。
それが今日の島原城薪能へと発展する。
4.伊能忠敬の島原領内測量と島原藩の地図作り
全国を測量して日本全図の作成を目指していた伊能忠敬は、1812(文化9)年島原領内を測量した。
この年11月4日、諌早領から愛津村(愛野町)に入り、半月かけて島原半島を一周、諌早領唐比村(森山町)へ去った。
一行10人(従者を入れるとて19人)は二手に分かれてくまなく測量した。
島原では別当家などへ5泊して、島原大変後に生まれた島原の島々には渡海して実測している。
また大崩壊した眉山の様子、大きく変わった海岸線を詳しく調べた。
これらは島原大変の科学的な解明に現在でも役立っている。
なお、島原藩では郡方役人を同行させて測量術を学ばせた。
なかでも奥村立助はその後測量方となって活躍する。
そして15年後には領内図や各村図を完成させた。
これらの地図は今でも伝わり、島原領内全図、中木場・安徳両村図などは伊能図同様に現在の地形図とくらべても遜色がない。
このように伊能測量の果たした意味は大きかった。
5.人体解剖図
1843(天保14)年、島原藩校・済衆館関係者によって死体解剖が行われ、その解剖図が島原城資料館に展示されている。
「医術の修業のために解剖して実物について研究したい。
門弟たちにも解剖術を伝授して医術の向上を図り、非命の病人を救いたい」と、済衆館教授・市川泰朴を中心に、藩庁に解剖を願い出た。
彼らは指揮・執刀・写生・秤量・磨刀・図書の係と役割を決め、今村の刑場で罪人の死体を貰い受けて解剖した。
門弟にも執刀させ、内蔵を測ったり記録したり、解剖図と照合したりと検証した。
翌年にも解剖してさらに研究を深めた。
展示されている解剖図を見ると、頭部から足先まで原寸大で描かれている。
臓器の形や色、重量なども正確で、「丈至肩4尺8寸、頭重10斤、小腸長さ2丈9 尺2寸周2寸5 分、大腸長5尺6寸5 分周5寸5分…」との記述のように、現在のレベルと比べても遜色がない。
改めて島原藩の医学の進歩に驚く。
この時、蘭学者の賀来佐之が大きく関わる。
6.天下の奇書・墨是可新話
厳しい鎖国時代にメキシコまで流されて帰国できた島原人がいる。
その人の名は島原の船乗り、太吉。
1841(天保12)年、房総沖で遭難して太平洋を漂い、スペイン船に助けられメキシコまで送られた。
中国を経て1845(弘化2)年、無事帰国できた。
この大旅行は『墨是可新話』という本にまとめられて、今でも島原図書館へ伝えられている。
彼は1799(寛政11)年頃生まれた。
島原城下片町に住んでいて、船乗りとして西宮中村屋の船・永寿丸に乗り込んでいた。
遭難して4ヶ月も太平洋上を漂うが救助されてメキシコへ運ばれ、この地で2年近く暮らす。
便船を得て中国へ渡るが、この地でも1年余。
太吉の帰国は城下町で大評判になり、「メシコ帰りの太吉どん」ともてはやされた。
藩校教授の賀来佐之は面談して、彼が体験した異国の様子を聞き取ってまとめたのが、上述の書物である。
今も伝わる同書には、遭難の有様や異国の珍しい様子、習慣が美しい挿し絵つきで述べられている。
またスペイン語の単語や会話文などが全7巻にまとめられていて、当時の人がいかに外国へ強い関心を持っていたかが良く分かる。
7.幕末島原を駆け抜けた松陰・海舟・龍馬
島原は九州のほぼ中央にあるから、長崎への通り道の一部になっていて、いろんな人が立ち寄っている。
吉田松陰は二度島原を訪れた。
1850(嘉永3)年に松陰が西国遊学に出た時、その帰路、11月2日に島原へ着いた。
島原では砲術指南・宮川度右衛門宅などで、島原藩の海防のことや兵器・砲術のことなどを学んでいる。
また温泉山へ上り、小地獄で入湯した。
1853(嘉永6)年、浦賀にペリー艦隊が入港したその後、今度は長崎にロシア・プチャーチン艦隊が入港したと聞き駆けつけた時である。
江戸から急行して熊本に立ち寄り、横井小楠たちと会って島原へ渡り、長崎へ急いだ。
しかしロシア艦隊は出帆した後だったので、もと来た道を引返して、島原から熊本へ渡る。
この時、外国への密航を思い立って長崎へ駆けつけたという。
どんな思いで島原を見、旅を続けたろうか。
坂本龍馬・勝海舟の来訪は1864(万治1)年のことである。
この頃は攘夷運動が高まり、国内政治は混乱していた。
アメリカなど4カ国連合艦隊は下関砲撃の報復を準備するなど、我が国は危機を迎えていた。
幕府の海軍奉行介にあった勝海舟は、連合国側との調停にあたるために坂本龍馬たち神戸海軍操船所の若者を引き連れて長崎へ向かった。
この時、熊本から島原へ渡海した一行は、島原城下本陣・中村孫右衛門宅に一休み、愛津村庄屋深浦家に宿泊した。
一月余り各国領事や提督たちと交渉するが不調に終わり長崎を去る。
帰路も野井村庄屋宅で一泊し、さらに島原町別当中村家で宿泊して熊本へ渡る。
今でもその跡をたどることが出来る。
上陸し離岸した島原湊の波戸、宿泊した城下本陣の屋敷門、庄屋宅の庭園などなど、その場にたたずむと、幕末を駆け抜けた坂本龍馬たちはこの島原はどう眺めたろうかと歴史のロマンをかき立てられる。
8.深溝世紀
この書物は歴代深溝・島原藩主の業績や領地の出来事をまとめたもので、島原藩の重要な歴史書の一つ。
明治維新で由緒ある「島原松平藩」が消滅することになり、そこで藩の歴史などをまとめて残そうと藩校・稽古館教授の渡部政弼(太平)を主任に、その編纂事業に取りかかった。
藩日記や諸記録をもとにして、家中にも呼び掛けて精力的に取り組み、明治7,8年(1874~5)ごろ終了。
島原松平家はその出身が深溝だから、書名を『深溝世紀』とした。
島原藩政の展開や知られざる島原地方の歴史が明らかとなり、それで「島原学」の研究に大きく役立っている。
初代忠定から最後の忠和まで全25巻、15冊となる。
編者の渡部政弼は最後の藩校教授で、その墓は晴雲寺にあり、大きな頌徳碑も建っている。
深溝松平家は三河松平7家の一つで、松平太郎左衛門が新田家の支族だった徳川親氏を女婿にしたことから始まり、松平家を相続して徳川太郎左衛門親氏と名乗る。
その子が松平家の主流となり、子の松平信光(その6代後が徳川家康)が応永28年(1421)頃、室町幕府の政所執事伊勢貞親の家臣となって安城や岡崎の城を攻略。
松平家の基礎を築く。
深溝松平家の祖先は松平信光の孫で松平忠景の次男、松平忠定。
深溝城を攻めて本拠地とした。
2代好景は44歳で戦死、3代伊忠は長篠の合戦時に鳶巣山の武田軍と戦かって死亡。
4代家忠は天正18年(1590)に徳川家康の江戸城領有に従い、武蔵忍城(1万石)へ、さらに下総上代城、小美川城へと移る。
慶長5年(1600)の関ヶ原合戦前哨戦の伏見城の戦いで戦死する。
3代にわたって徳川幕府成立のために命を捧げた。
5代忠利は三河西郡城、吉田城主(3万石)となり、6代忠房はこれを継ぎ、三河刈谷、丹波福知山城(5万石)、そして寛文9年(1669)肥前島原城主(6万5900石)となる。
(次回は「第5回 明治の新しい世」)
先生の紹介
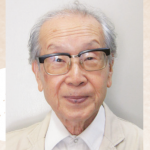
過去の記事はこちら。
島原の歴史50選「第3回 松平時代」
島原の歴史50選「第2回 切支丹時代」
島原の歴史50選「第1回 原始・古代・中世」
「人物・島原の歴史シリーズ 第6回 未来へ続く人々」
「人物・島原の歴史シリーズ 第5回 新しい時代を切り開く」