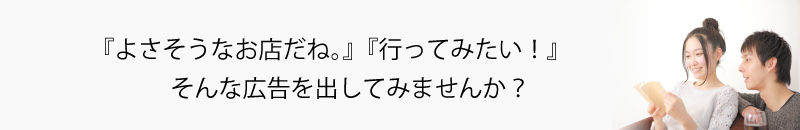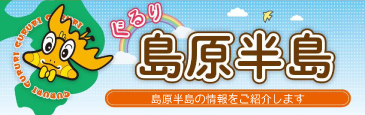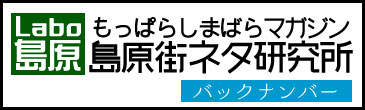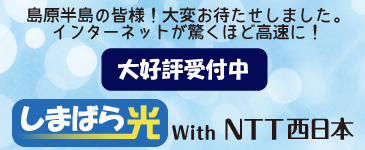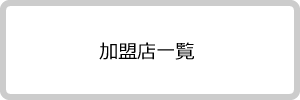松尾先生は昭和10(1935)年島原市生まれ。
島原城資料館専門員、島原文化財保護委員会会長。
『島原の歴史については松尾先生に聞け』と言われる島原の生き字引的存在。
著書に『おはなし 島原の歴史』『島原街道を行く』『長崎街道を行く』など。
※FMしまばら(88.4MHz) 毎週水曜日 12:05~「松尾卓次の島原歴史探訪」放送中!
記事
12.202015
松尾先生の島原の歴史50選「第5回 明治の新しい世」
1.廃藩置県
1867(慶応3)年、将軍慶喜が大政の奉還を上奏した頃には島原藩主は病床にあって、「城内では大吟味で昼夜相詰めて…、色々評論に相及び…」との状態であった。
やっと家老・板倉勝直が上京して朝廷に忠誠を誓うのである。
そして奥州出征を命じられた。
島原藩では159人が大砲2門を引いて1868(明治2)年8月から12月まで参戦して戦死者4名を出す。
翌1869年4月、藩主が上京して版籍の奉還を願い出て、その返上が認められた。
ここに有馬氏以来2世紀半に及ぶ島原藩政が終わった。
1869(明治2)年の版籍奉還で、忠和藩主は島原藩知事に任命された。
1871(明治4)年には島原県にと替わり、藩知事は免職となって東京へと去る。
この年11月には長崎県へ編入されて島原藩庁跡に県の出張所が置かれた。
この頃の島原半島は石高約3万8000石、領民12万8000人余、士卒族6500人余。
それに神代鍋島領1100石、3000人余が加わる。
この1年前には各町村の別当・庄屋制度が廃止された。
2年後には新しい行政区が制定された。
その後2町28村にまとまる。
2.島原城解体
廃藩置県で無用の長物となった島原城は、1871(明治4)年から民間へ払い下げられた。
「なにせ築城250年もたっているので年々の修理経費も少なくなく、廃棄して無用の雑費を省き、実用の軍資に備えたい」と、政府への上書が認められ、入札払いが始まった。
先ず大手門が解体され、旧御殿や諸道具が入札に付された。
とうとう5層の天守閣も1876(明治9)年には解体されてしまう。
その前年には天守閣の見物が自由となり、多くの町人・農民が登閣した。
この払下げ代金は、合計519円50銭であった。
250年の間にはいろんな出来事があった。
島原の乱時には農民軍が押寄せて激戦が続いたが落城を免れた。
島原大変では何度も大地震に見舞われ、大津波が外郭石垣まで打ち寄せたが安泰であった。
しかし時代の波には抗することが出来ず廃城・解体となった。
なんとその天守閣の柱の一部がある旧家に伝わっている。
柱の一部や箱書きに「天和2年島原森岳城松倉豊後守重政公築城、その時天守柱間梁立13間余、下柱72本、この内6本は五重上階に出る。
北有馬村北岡天満宮御庭松の内9本立る、その内この品なり。
後年天守柱と申し伝える。
明治9年秋 清水武衛」その後約百年間、本丸と二の丸の外郭は残り、石垣と堀だけの裸の城であった。
三の丸御殿跡は小学校と中等学校に払い下げられ次世代の教育に大きく役立っていく。
3.口之津貿易港
口之津は有明海の出入り口にあるから港で栄えた。
古くは1562年からは南蛮船が入港し、世界へとつながる。
藩政時代には、「この湊は長さ12町、横8町、深さ7尋…船掛り場所は回船千嫂分ほどあり…」といわれて、潮待ち、風待ちの船で賑わっていた。
近代になると世界へ開かれた貿易港となった。
対岸の三池炭は、以前から西日本各地へ売り出されていた。
瀬戸内の製塩業に盛んに利用されていて、その輸送を引き受けていたのが島原湊の山本屋であった。
さらに明治となり、取り引きが自由になると、三井会社はアジア各地へ石炭を輸出し始めた。
三池には良港がないから、口之津港から積み出された。
1896(明治9)年、貿易港に指定され、その第一船がシャンハイへ出港した。
以来輸出が伸びて、最盛期には年間92万tの石炭が輸出された。
貿易額350万円、入港船舶2900隻にもなった。
1909(明治42)年に三池港が完成したら、次第に口之津港は衰退した。
三井の成長は口之津港からといわれるほど大きな役割を果たした。
今、その税関署跡に「南島原市口之津歴史民俗資料館」が開かれ、口之津が港と共に栄えてきた歴史と、海に係わった人々の生活を伝えている。
4.島原中学校と島原高女・口加高女
「学制」の発布で小学校教育が始まった。
1873年、島原では町の有力者が2,000円の基金を集め、島原城三の丸御殿跡に「一番学校」を、新町別当宅に「二番学校」、湊に「三番学校」を開校した。
しかし学校開設は各村にとって大きな負担であった。
深江村では小林治市が自力で学校を建設し、設備とともに村へ寄付した。
この熱意と功徳に感謝して、校名を「小林小学校」と決めたほどである。
小学校教育が軌道に乗ると、中等学校設立の動きが高まる。
このために郡内各町村は建設費用を拠出し、旧島原藩主には敷地と建物など一切を寄贈してもらい1900(明治33)年9月、県立島原中学校が開校した。
翌1901年には私立島原女子手芸学校も開校した。
これは町の素封家・清水作次郎が私財5,000円と旧三の丸一角の私有地1000坪を投じて創立したもの。
島原中学校の創立にかかわった氏は、女子中等学校を早急に実現するには私人の力によるほかはなしと決意した。
その創立は県下でも3,4番目と早い。
やがて郡立・県立島原高等女学校となる。
同様に1902年には、永野仲蔵が私財を投じて私立口之津女子手芸学校(口加高校の前身)を開いた。
この3つの中等学校は、島原半島内の教育に計り知れないほど大きな恩恵をもたらすのである。
卒業後はさらに上級校へ進む者も多く、島原高女では10%となる。
5.ファーストジャパニーズ
藩政時代は宗門改めが厳しかったから、離村は難しかった。明治の御一新で自由になると、仕事を求めて海外へと出る人も多く、先駆者となる。
それが島田元太郎、永野万蔵である。
ロシアへ渡った島田元太郎
土黒村(国見町)出身の島田元太郎は15歳でロシアへ渡り、1897(明治29)年ニコラエフスクで島田商会を開業。
その後事業を拡大させて、年商2700ルーブル(現在の1兆円余)をあげていた。
島田札と呼ばれた同商会の商品券はルーブル札より信用が高かった。
この地はアムール川河口にあって、沿海州やサハリン(樺太)との物流の中心地である。
この地に目をつけて、雑貨販売、鉄工業・造船、金鉱開発、銀行・金融業など総合商社にあたるような経営である。
ロシアの産業や日本・ロシア貿易に大きな役割を果たしていた。
しかしロシア革命が起こり、パルチザンのために1920(大正9)年当地の日本人が虐殺される出来事(尼港事件)が発生、島田商会も壊滅的な打撃を受けた。
この時、島原半島出身者が65人も死亡したから、関係が深かった地元では大問題となった。
翌年再開するが、ソビエト政権成立で撤収せざるを得なくなる。
すべてをなくした彼は、戦後の混乱時期にピョンヤンで、その波乱に富んだ一生を終わる。
カナダ移民第1号永野万蔵
日系カナダ百年祭が開かれた時、永野万蔵が1877(明治10)年にニューウエストミンスターへ上陸したのを、日本人移民の始まりと決定した。
日加友好のモニュメントとしてバンクーバ市郊外の高峰に「マウント・ナガノマンゾー」と命名している。
永野万蔵は口之津村に1855(安政5)年頃生まれた。
18歳時からイギリス船に乗り込んでシャンハイやホンコン、ボンベイなど各地へ渡った。
そしてカナダへ着き、密入国する。
漁業や港湾人夫として働いて元手を蓄え、シアトルで雑貨店を開く。
さらにレストランやホテルなど手広く営業し、塩サケの製造・輸出でさらに利益を上げた。
それでカナダ大尽と呼ばれ、当地の日本人会の会長にもなった。
しかし第一次世界大戦後の世界恐慌時に火災にあい、さらにスペイン風邪に冒される。
失意の中で帰国して、口之津で養生するが叶わず、70年の生涯を終わった。
6.島原の文明開化
島原地方にも文明開化が鉄道に乗ってやってくる。
同時期に文明の光が地方を照らす。
それは植木元太郎と城台二三郎の活躍の成果だ。
国に頼るだけでなく、地方で出来ることは自分たちの力でやり抜こうという精神である。
それで島原地方の二人の巨人と呼ぼう
<文明の光・千々石発電所>
千々石村の素封家城台二三郎は千々石川の豊かな水量に着目して水力発電の開始を思い付き、1909(明治42)年、資本金8万4000円で「小浜水力電気合資会社」を創立。
郡内一円と近くへ供給する電気事業を始めた。
これは長崎県下初の営業用水力発電所である。
水圧管、水車、発電機、配電線など資材一切をドイツシーメンス社から購入して、浜から木場地区まで道を切り開いて運び入れる。
そして木場一色に発電所を造り、55kWの電気を起こし、1910(明治43)年に島原半島最初の電灯が灯った。
島原3町村698戸は明るいお正月を迎えることが出来た。
その後島原水電株式会社へ組織替えし、資本金も増資した。
電灯は瞬く間に郡内各地へ広まり、文明の光が各家庭を照らした。
その後発電所を5か所、火力発電所も造り需要にこたえた。
しかし増大する電気消費量には追いつかず、1930(昭和5)年、熊本電気株式会社に吸収合併された。
この時、需要家数3万171戸であった。
今でも5つの発電所は活躍、電力を送り出す。
その量は千々石町の消費電力の4分の1しかならないが、けなげにその役割を務めている。
<島原鉄道の開通>
1911(明治44)年6月22日、島原半島を始めて汽車が走った。
最初は諌早・愛野間であったが、2年後には島原湊まで42kmが全通した。
鉄道の開通は島原半島の人々や町村に計り知れない恩恵をもたらした。
島原の文明開化はここに始まったといっていいくらい。
そのもとが、1906(明治39)年に在京の旧藩士らが出した「島原鉄道敷設趣意書」である。
「物資の集散地である島原湊から本土へ、石炭輸出地の口之津、全国無比の名湯、小浜・温泉(雲仙)を結ぶ3本の鉄道を建設し…」と、訴える。
1908(明治41)年、島原鉄道創立総会が島原町で開かれて植木元太郎を社長に選び、資本金90万円で始める。
1913(大正2)年に島原鉄道が諌早・島原湊間に全通する。
この時走った機関車が、あの日本で初めて東京・横浜間を走った機関車で、島原でも一号機関車として20年間活躍する。
国の重要文化財として鉄道博物館へ保存・展示中。
次は南目鉄道の話が持ち上がる。
1919(大正8)年口之津鉄道創立総会が開かれ、建設費70万円で島原湊・口之津間に鉄道を敷設することを決め、社長に植木元太郎を選びスタート。
1928(昭和3)年には加津佐まで全線36kmが開通した。
さらに支線として愛野・小浜間の計画は、やっと1918(大正7)年に小浜軽便鉄道目論見書がまとまる。
18.6㎞、建設費35万円と打ち出した。
1923(大正11)年には愛野・千々石間9kmが開通した。
1927(昭和2)年には千々石・小浜北野間8kmも開通した。
一時4つの鉄道が走るが、それが今では島原鉄道北目線のみとなる。
<島原新聞>
これら島原地方の情報を伝え、地域を導き、知的文明開化となるのが島原新聞(当初は開国新聞)で、1899(明治32)年8月25日創刊。
島原町で清水繁三により旬刊紙を発行、日露戦争の頃には日刊紙となる。
しかし戦後不況で廃刊となり、付録紙の発行となる。
1913(大正2)年「島原新聞」と名を変えて再発行。
戦時中の言論統制で1942(昭和17)年県1紙の「長崎日報」に統合されるが、戦後1946(昭和21)年12月、再び「新島原新聞」として復刊、現在の「島原新聞」へと至る。
一地方紙が百年以上も続いているのは全国で2、3紙しかない。
これも地元に密着した紙面作りに徹して特色あるローカル紙として、その存在を発揮しているからである。
地方の歴史を記録し、近現代史料の宝庫となる。
7.盛んな養蚕・製糸業
政府の殖産興業政策で、島原地方でも養蚕業が発達した。
江戸時代から盛んだった木綿織物業の地盤があったからこそ、明治になるとさらに栄えるのである。
旧藩士の草野覚徳は士族の授産事業として本格的に養蚕業を始め、先進地へ出かけて研究、技術の導入を図って、その推進者となった。
明治中期(1880年頃)で繭313石の生産を上げ、生糸の生産は160貫目、6,100円の利益を得た。
雲仙岳の風穴(火口跡)は天然の冷蔵庫であり、蚕の保存場に良いと活用されていた。
10万枚の蚕種を作り出し九州各県へ売り出していた。
製糸業も進み、大正末から昭和初年には8つの工場が操業して、二百数十万円の生産をあげていた。
1928(昭和3)年の調査では繭の生産56万貫目、335万円の産額であり、これは県内生産の6割を占めている。
養蚕業は農家の良い副業として村を潤した。
そこで県では島原町に養蚕試験場を置き、養蚕取締所を開き、新しい技術を持つ技術者の養成を図り、養蚕業の発展に努めた。
(次回は「第6回 激動の時代」)
先生の紹介
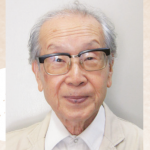
過去の記事はこちら。
島原の歴史50選「第4回 しまばらの江戸文化」
島原の歴史50選「第3回 松平時代」
島原の歴史50選「第2回 切支丹時代」
島原の歴史50選「第1回 原始・古代・中世」
「人物・島原の歴史シリーズ 第6回 未来へ続く人々」
「人物・島原の歴史シリーズ 第5回 新しい時代を切り開く」