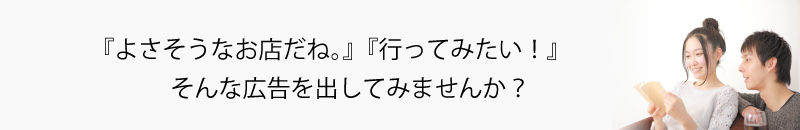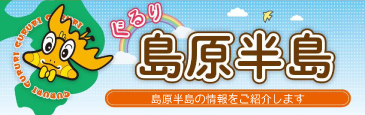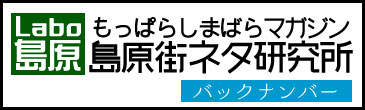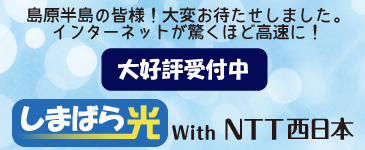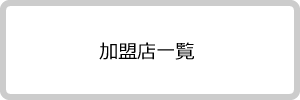松尾先生は昭和10(1935)年島原市生まれ。
島原城資料館専門員、島原文化財保護委員会会長。
『島原の歴史については松尾先生に聞け』と言われる島原の生き字引的存在。
著書に『おはなし 島原の歴史』『島原街道を行く』『長崎街道を行く』など。
また毎週月曜日午後12:05時~、島原のラジオ局、FMしまばらで『島原の歴史』を語っています。
記事
4.222015
松尾先生の島原の歴史50選「第1回 原始・古代・中世」
各地にはそれぞれ長い長い人々の歩みがある。
私たちの島原にも数千、数万年も昔から現在までの長い歴史がある。
その中から厳選した50話を紹介したい。
1.旧石器時代の島原
日本列島に人類が住むようになったのは約50万年前のことといわれている。
アジア大陸から、マンモスなど大型動物を追ってやってきた人たちが住みついた。
当時、有明海は湖か平原であったようで、そこに住んでいたナウマン象の歯の化石が発見されている。
その頃から島原半島には人々が居住 していた らしい。
雲仙市国見町百花台には、旧石器時代から縄文時代にかけての遺跡がある。
台形石器などが多数発掘されて、今から26,000年前から長期にわたって生活が営まれていたことがわかる。
旧石器時代から縄文時代に至る遺跡で、ナイフ型石器、台形石器、細石器と石器の変化が明らかになり、中でも台形石器は「百花台型」と名付けられている。
この石器を数個組み合わせて槍の穂先に使用して、狩の能率を上げていたようである。
同時代の遺跡として、島原市三会礫石原、南島原市北有馬町諏訪などがある。
2.縄文~弥生時代の島原
1万年前頃、土器が使われるようになると人類は食生活を飛躍的に発展させた。
またこの頃、気候の温暖化で照葉樹林が分布を広げてきて、大型動物は北方へ去り、人々はこの森林に多くできるドングリなど木の実に目をつける。
豊かな実りを目前に、いかにして食べるかを工夫した結果が土器の発明へとつながった。
この時代を縄文時代と呼ぶ。百花台遺跡からは縄文時代早期の炉の跡が見つかっている。
また押型文の土器や石器類も出土して、これらの道具を使って狩猟と採集の生活をしていたことがわかる。
礫石原には2m四方に石を敷き詰めた環状石組遺構があり、埋葬祭祀共同体を構成するもので重要な遺構といえよう。
同時代の遺跡として、三会礫石原、南島原市深江町山の寺、同北有馬町諏訪、雲仙市吾妻町弘法原などがある。
縄文人は長年かけて生活を向上させて人口も増えた。
それで狩猟や自然採集では間に合わず食物獲得が問題となる。
今から2,300年前に大陸から稲作技術を持った人たちがやってきて生産経済へと変えていった。
それで食糧確保が容易となり、安定した生活ができるようになった。
この新しい時代を弥生時代という。
またこの時代には金属器も伝えられ、原始の世を文明の時代へと変革させた。
南島原市北有馬町原山には支石墓(ドルメン)が集中していて、これを作った人たちは日本に稲作を伝えたといわれる。
島原半島は大陸文化受け入れの中継地点にあたる。
この時代、低湿地や川の下流の沼地で米作りが盛んに行われた。
しかし島原半島では大きな平野に恵まれないので、北部九州や近畿地方のように米作りを生産基盤にすることはできなかったようだ。
縄文時代の伝統を引きずって半農半漁的な生活をしていたのではないか。
つまり春から秋にかけて米作りの作業をして、冬から春の始めには海で貝やカキなど貝類を、森でドングリなど木の実を採集して、貯蔵に精を出していたと思われる。
3.古墳時代の島原
米作りは、社会を大きく変えていく。
人々は水田を中心に小さな集落に集まってムラをつくり、そのムラをまとめ指導するカシラが生まれた。
さらに生産が向上すると、力の強いカシラが多くのムラをまとめてクニと呼ばれる小国家が誕生する。
弥生時代中期になると各地のカシラは豪族となって、土地や人民を奪い合い、戦乱を繰り返しながら次第にその地方を統合していった。
それが邪馬台国であり、このような小国家が北部九州や近畿地方にかけて多く生まれた。
3世紀には畿内勢力による国家統一が始まり、近畿地方から瀬戸内地方にかけて豪族の墓である巨大な古墳が築造される。
この時期を古墳時代といい7世紀まで続く。
4世紀にはその統一政権は九州にも及び、各地に壮大な前方後円墳も築かれるようになった。
島原半島では遅れて、6世紀になって古墳が出現する。
雲仙市吾妻町守山には大塚古墳がある。
島原半島唯一の前方後円墳で大きく、ほぼ原形が保たれている。
築造時期は5世紀後半から6世紀初期であろう。
後円部直径約45m、中央部高さ7m。
前方部長さ25m、幅20m、高さ2.7mある。
同市国見町多比良には高下古墳がある。
6世紀中頃に築かれ3代にわたって追葬されているようだ。
大型の横穴式古墳で、2mから3mもの巨石をいくつも使っていて豪族の権力の大きさが偲ばれる。
この2つの古墳から島原半島の支配権力の推移が推定されて興味深い。
4.肥前国風土記にみる島原
大和王権が全国をほぼ統一すると天皇の勢力が強まり、中央の豪族をまとめて政治の仕組みを整えていった。
唐(中国)の律令制度を取り入れて天皇を頂点とした中央集権国家がつくられた。
島原半島もその中に繰り込まれる。
長崎・佐賀両県は肥前国といい、その中に高来郡、彼杵郡、松浦郡など11郡があった。
さらに高来郡の中には9郷、也万田(山田)、爾比井(伊古か伊福)、加無乃呂(神代)、乃止利(島原)などの存在が分かっている。
郡衙(郡役所)は国見町多比良に置かれていたろう。
また駅が18か所あって、それらを結ぶ道が官道として整備された。
国府(佐賀県大和町)から出発し長崎県内に入り、新分、船越、山田、野鳥の駅へ続き、渡海して肥後国へと結んでいた。
8世紀初めに編集された「肥前国風土記」には、高来の地名が高来津座、つまり高い峯・温泉(雲仙)山に居を構える土着神(豪族)がいたことによる。
温泉山とそこから湧き出る温泉の存在など1,300年前の島原の様子がよく分かる。
5.温泉山信仰
高来の峯は古代から知られた温泉の山である。
そこには地方を統治する神・豪族が君臨し人々の信仰を集めていた。
701(大宝元)年、僧行基によって温泉山満明寺が創建された。
古くからの霊地であって巡礼の山であった。
温泉山は険しい山中にあって登山は容易でない。
参拝が簡単に出来ないので山麓に4分社が置かれた。
その分身末社に山田神、有江神、千々石神と伊佐早神が座した。
ここに温泉神社が創建された。
祭神は白日別命、豊久士比泥別命、豊日別命、建日別命の4神で、筑紫国、肥国、豊国、熊曽国の九州4神を祭ったので別名四面宮とも呼んだ。
温泉山信仰は隆盛を極めたが、今もその名残が島原半島各地に見られる。
またつい先年までは「温泉詣で」といって,年に一度は普賢岳にお参りしていた。
6.中世の島原・武士の成長
奈良時代に天皇中心の中央集権政治が隅々まで行き渡り律令政治が仕上がった。
その後、古代律令国家は崩れはじめ、都が平安京へ移され平安時代となる。
公地公民制度は乱れて、貴族や寺院は多くの特権を得て土地と人民の私有を進めた。
こうして荘園制度が生まれ律令体制が根底から崩壊 していく。
藤原氏が政権を独占して政治が乱れて社会不安が続いた。
地方では、豪族たちは所有地を守るために武装して武士団が生まれた。
やがて地方政治は、これら武士による農民支配を基盤に展開するようになり新しく政治権力を持つ。
源頼朝が武家政権を樹立すると島原半島でも荘園が見られ、そこから豪族・武士が生まれた。
時代とともに荘園は増えて13世紀には高来郡内に、山田庄240丁(町)、髪白庄40丁、高来有間庄80丁、串山庄20丁、千々岩庄30丁、伊佐早庄253丁があり、公田として高来東郷245丁、高来西郷83丁と記録されている。
こうして中央の政治は地方に及ばず、各地の豪族や領主が支配権を持ち始める。
武家政権では、将軍の下に御家人(武士)を結集して全国を統治するようになる。
各地の豪族が在地領主となり、御家人が地頭となって各地へ下向して支配する。
千々石の林田氏、吾妻の矢俣氏、瑞穂の綾部、大川、伊古、伊福の各氏、国見の神代氏と多比良氏、有明の大野氏、島原の島原氏などの名が在地領主としてみられる。
下向した御家人としては、藤原経澄が有間庄地頭、野本行員・時員兄弟が深江の地頭職、安富頼清が深江庄の地頭になっている。
各地の御家人や領主、豪族たちは領地の拡大を求めて抗争を繰り返した。
中央政権の権威が崩れると戦乱の時代が続いた。
島原半島各地にいた豪族の中から、この戦乱を通じて有馬氏が成長して一円を支配するようになる。
7.有馬氏の一円支配
有馬氏は鎌倉御家人で、1215(建保3)年に有間庄地頭として常陸国から下向して、所領した地名をとって有馬氏と名乗った。
しかし、有馬氏は古代から続く豪族であるという説もある。
島原半島南部を根拠地とした海運に従事した豪族であったかもしれない。
有馬連澄は1346年に日之江城を、貴純は1496年に原城を築いたという。
いずれも戦乱の時代で、島原半島の覇者となった頃である。
混乱は続き、足利尊氏が室町幕府を開いて武家政権の存続をはかるが、天皇側と争う南北朝内乱期を迎える。
この時期九州では、熊本の菊池氏を中心とする宮方(天皇側南朝勢力)と九州探題一色範氏を中心とする武家(幕府側北朝勢力)が争っていた。
島原半島でもそうで、宮方に多比良、神代、西郷の諸氏が、武家側に有馬、安富、伊佐早の各氏がそれぞれ加わって対立した。
懐良親王が征西将軍に任命されて菊池に入り、島津氏を破ると宮方勢力が伸びる。
直冬が九州に下向して一色氏と対立すると宮方、武家方、佐殿の三者に分かれて戦うようになり混乱を深めた。
各地の豪族も戦乱に巻き込まれて動きが活発となる。
この時期、多くの城(砦)が築城された。
1359年には九州の有力武将少弐頼尚軍が懐良親王・菊池武光軍と筑後川大保原で合戦し打ち破る。
この戦闘は九州の南北朝戦乱最大の合戦で、九州各地の豪族が続々と参戦し、武家側に有馬房澄、宮方に安富泰重・泰治たちが加わっていた。
その後、菊池武資が宮方勢力の挽回を図って島原半島の奪還を図るが、大浦城で敗北、ここに島原半島での戦乱が終わる。
半世紀にわたる南北朝内乱期に、島原半島の豪族や武士たちは戦闘と和睦を繰り返して盛んに離合集散していった。
だれを主君、棟梁とするかは全く自由で、御家の存続を賭けて、その時々の利害に敏感に反応して勢力拡張をもくろんだ。
島原半島でも多くの在地領主がいたが、その中から有馬一族が勢力を伸ばして、彼等を家臣として取り込んで大名へと成長するのである。
有馬晴純は肥前国守護職ともなる。
- 岩戸・修験道場
- 雲仙・温泉神社
- 大野原(有明)の発掘調査
(次回は「第2回 キリシタン時代」)
先生の紹介
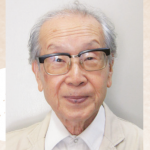
過去の記事はこちら。
「人物・島原の歴史シリーズ 第6回 未来へ続く人々」
「人物・島原の歴史シリーズ 第5回 新しい時代を切り開く」