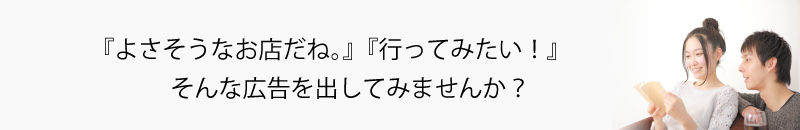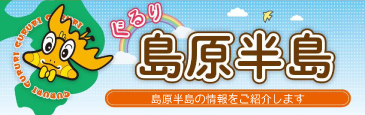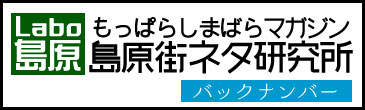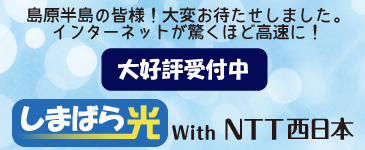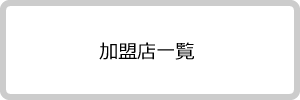人物・島原の歴史シリーズ
-
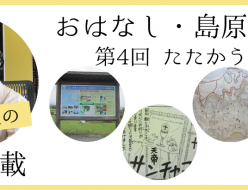
6.212018
松尾先生のおはなし・島原の歴史 第4回 たたかう金作
〈はじめに〉必ず歴史の教科書に書かれている「島原の乱」。島原市三会地区にはその伝承が残る。三会村には「下針金作」という鉄砲打ちがいて、数間離れた針のメンズ(穴)も打ち抜くことができるといわれた名人であった。島原の乱では三会の村人を引き連れて参加、大活躍。
-

4.192018
松尾先生のおはなし・島原の歴史 第3回 いのちある限り
?〈はじめに〉セミナリオの町カラーン、コロン、カラーン、コロン、、、、。教会のカネが鳴っています。ここは有馬の城下(今の北有馬)です。有明海に白いお城が写っています。その青い静かな海をカネの音がどこまでも広がっていきます。それは昨年の事でした。
-
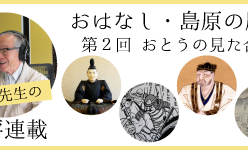
2.192018
松尾先生のおはなし・島原の歴史 第2回おとうの見た合戦
〈はじめに〉有馬の殿様島原半島は肥前の国から有明海に突き出たところにあります。まわりを海にかこまれ、一つの独立した地域になっています。この地を有馬氏が長く支配してきました。そのもとは藤原経澄といい鎌倉武士で、地頭となってやってきました。
-
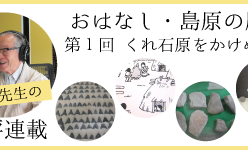
12.212017
松尾先生のおはなし・島原の歴史 第1回くれ石原をかけめぐる
〈はじめに〉各村や町にはそれぞれ長い人々の歩みがあります。私たちの島原にも数千、数万年の歴史があります。今から数万年もの昔の人が使っていた石器が三会町から発見されました。こんな大昔から島原の歴史が始まったのです。
-
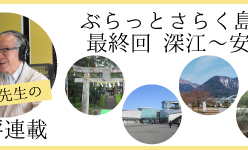
10.202017
松尾先生のぶらっとさらく島原 最終回 深江~安中
〈はじめに〉両地区とも今次災害で大きな被害を受けた。その後の復旧で同じ行政体となり、共に復興策を進めていくものと思っていたが、そうはいかず、、、。両地区ともに災害の歴史を繰り返してきた地で、さらいてみると災害の爪痕は依然として残っている。
-

8.232017
松尾先生のぶらっとさらく島原 第9回 有家~布津
〈はじめに〉有家は大きな町である。またその成り立ちは複雑で、島原の乱時は有家村といい、今の有家・西有家を含んでいた。その後、有田村・有家町村・隈田村に分かれ、それぞれに庄屋が置かれていた。明治になってその3村は合併し、1879年に再び東有家村と西有家村に分離した。
-
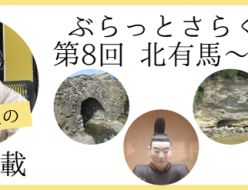
6.202017
松尾先生のぶらっとさらく島原 第8回 北有馬~西有家
〈はじめに〉有馬氏のこと街道は春日神社前を通る。ここは有馬氏の氏神様で、有馬氏の先祖は藤原純友といわれるから、一族は奈良・春日大社を勧請して分霊した。また日野江城下を通る。有馬氏の居城で、1215年に藤原経澄がこの地に地頭として入国し、土地の名をとって有馬と称した。
-
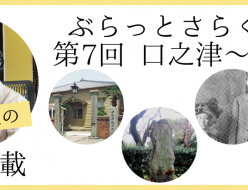
4.192017
松尾先生のぶらっとさらく島原 第7回 口之津~南有馬
はじめに口之津は港で栄えた町である。有明海の入り口にある津(港)ということからその名が生まれたろう。有明海は大きな内海で、沿岸に熊本、柳川、佐賀の町があり、そこへ?がる口之津は格好の港である。
-

2.192017
松尾先生のぶらっとさらく島原 第6回 南串山~加津佐
はじめに3~4月は、雲仙市南串山町と南島原市加津佐町をさらく。藩政時代の西目筋である。南串山は一帯に傾斜の激しい丘陵地が広がり、そこには階段状の田や畑が重なり、どの田畑もよく手入れがなされている。
-

12.202016
松尾先生のぶらっとさらく島原 第5回 千々石~小浜
はじめに千々石町は大きな町である。それはまた歴史の古い地である。島原地方が初めて国中に紹介されたのは『肥前国風土記』で、そこには千々石の項がある。愛野町の原口番所跡から出発。ここは南目道の出入り口になっていて、関所が置かれていた地。