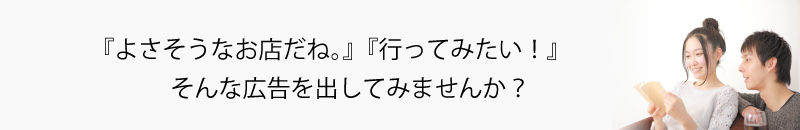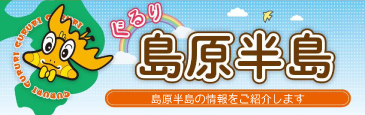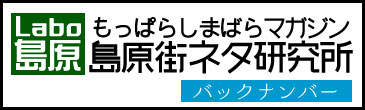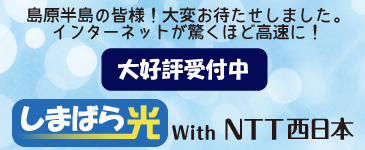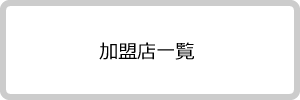記事
6.232015
島原市シティインフォメーション
嶋原松平家のルーツを紐解く 幸田町への友好親善訪問

嶋原松平七万石の城下町を語るとき、愛知県幸田町の深溝(ふこうず)松平との交流を語る必要があります。
1669年、徳川4代将軍家綱の命を受けた丹波国(福知山)城主の松平忠房公は、誇り高き三河武士の血を受け継いだ武将でありました。
遠く肥前の嶋原へ赴くために、三河の地の家臣多数とともに移封して来ました。
島原の乱後の平定と切支丹一揆などによる外国勢力を心配する徳川幕府は、譜代大名である忠房公に日本唯一の貿易港である長崎出島の監視と外国船の動向、そして諸外国の情報を江戸へ報告するよう命じました。
その際、豊後国(豊後高田)3万石を島原と合せて領地とするよう配慮しました。
嶋原松平7万石の誕生であります。
以来、途中で下野(栃木県)宇都宮藩の戸田氏2代との国替えをはさみ、松平氏13人が明治維新まで島原を治めて来ました。
その間、1792年の眉山の大崩壊による「島原大変肥後迷惑」もありましたが、ハゼの木を植樹し木蝋を生産するなど、産業を起こし財政を建て直し、また、能を庶民に公開するなど、文化を広めた善政の時代でありました。
今でも肥前松平文庫は、貴重な県指定の文化財であります。
そして、この松平一族は、常に故郷を大事にする一族であり、13人の全ての殿様の亡骸を幸田町まで運び本光寺に手厚く埋葬され、今でも見事に管理されております。
そこで、今年10月31日から11月1日までの2日間、市民100人で愛知県幸田町を訪問し、松平家ゆかりの歴史に触れてまいります。
当地では、「徳川家康公四百年祭」も行われており、楽しみであります。
一般公募は、8月から行う予定にしています。
広報しまばらなどでお知らせしますので楽しみにしてください。
市民の皆様も私と一緒に三河の地を訪れて見ましょう。